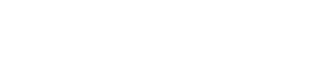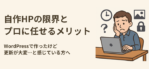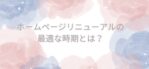Webマスター
求職者を惹きつける! 採用サイトに必要なコンテンツと効果的なポイントを紹介
2025年03月31日 8:00 2025年04月01日
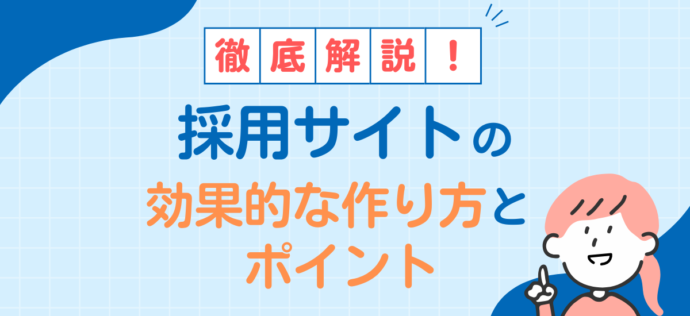
こんにちは、Webデザイナーのhrです。
3月も終わり、いよいよ新年度がスタートしますね。
新入社員の採用活動も本格化し、企業にとっては重要な時期です。
また、就職活動をしている皆さんにとっても、これからのキャリア選びにとって大切な時期となることでしょう。
「採用成果を上げるカギは効果的な採用サイトにある」と言われていますが、では、どんな採用サイトにすれば良いのでしょうか?
今回の記事では、採用を成功に導くための採用サイトのコンテンツ要素やポイントを紹介します。
採用活動で成果を発揮するための採用サイト制作のコツをお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
採用サイトとは
採用サイトとは、求職者に向けて自社の情報を発信するためのWebサイトのことです。
リクルートサイトと呼ばれることもあり、新卒採用や中途採用と分けて制作することもあります。
求職者が採用サイトを見る際は、少なからずその企業に興味があるということです。
採用サイトを通じて、求職者が企業に対する興味を深め、応募につなげるためには、魅力的で効果的なサイト制作が重要です。
採用サイトの重要性と役割
採用サイトは、求職者に対して企業の魅力を伝える重要な情報発信の場です。
学生や求職者は応募前に必ずといってよいほど、企業の採用サイトやコーポレートサイトをチェックし、必要な情報を収集します。
採用サイトに、企業理念や事業内容、職場環境、社員の声などが分かりやすく掲載されていれば、入社後のギャップを防ぎ、採用のミスマッチを避けることができます。
求める人材を獲得するための情報発信
優れた人材を惹きつけるためには、企業の強みや特徴をしっかりと打ち出すことが重要です。
例えば、独自の技術力や革新性、働きやすい職場環境や充実した福利厚生をアピールすることで、求職者の関心を引き寄せることができます。
さらに、採用サイトでは求める人材像を明確に示すことが重要です。
職種ごとの求人情報や必要なスキル、経験を詳しく掲載することで、理想的な人材との適切なマッチングを促進できます。
企業の存在を認知してもらえる
採用サイトは求職者だけでなく、顧客や取引先、一般の人々にも企業のイメージを伝える重要なツールです。
企業の価値観や文化、社会的責任への取り組みを積極的に発信することで、企業の認知度を高め、ブランドの向上にも繋がります。
例えば、社員インタビューや座談会の動画を公開することで、働く人々の生の声を通して企業の魅力を伝えられます。
また、社会貢献活動や環境保護への取り組みを紹介することで、企業の社会的責任をアピールできます。
魅力的な採用サイトを作ることで、優秀な人材の獲得だけでなく、企業の存在をより広く認知してもらうことができるのです。
採用プロセスにおける効率化と最適化
採用サイトは、採用プロセスの効率化と最適化において大きな役割を果たします。
応募フォームや適性検査、面接の日程調整などをオンラインで完結できるため、手間や時間を大幅に削減できます。
さらに、採用サイトにチャットボットやFAQ機能を導入すれば、求職者からの質問に自動で対応でき、採用担当者の負担を軽減できます。
さらに、応募者データの分析を通じて、採用活動の改善点を洗い出し、より効果的な採用戦略を立てることが可能になります。
採用サイトのデザインポイント

採用サイトのデザインにおける3つの重要なポイントを解説します。
これらの要素を効果的に組み合わせることで、魅力的で訴求力のある採用サイトを作り上げることができます。
ユーザビリティと使いやすさの確保
採用サイトでは、応募者が求める情報に簡単にアクセスできるよう、直感的で使いやすいナビゲーション構造を採用することが重要です。
具体的には、トップページに企業理念を一文で表現したキャッチコピーを配置し、応募者の関心を引きます。
また、重要な情報は階層的に整理し、視線誘導を意識した情報の配置を行います。
余白をうまく活用することで読みやすさを向上させ、コンテンツをグループ化して情報の整理を図ります。
さらに、スクロール位置に応じて適切な量の情報を表示する調整や、クリック操作で詳細情報を展開できるインタラクティブな要素を取り入れることで、使いやすさを向上させ、応募者の満足度を高めることができます。
ナビゲーションボタンの配置にも工夫を加え、応募者が次のステップへとスムーズに進めるように導くことが求められます。
魅力的なビジュアルとカラースキームの選定
魅力的なビジュアル要素は、採用サイトにおいて非常に重要です。
企業理念やブランドイメージを一目で伝えるために、写真やイラスト、動画などを効果的に活用しましょう。
例えば、ファーストビューには生き生きとした社員の表情を大きく掲載し、職場の雰囲気を直感的に伝えることができます。
また、企業理念を表現する写真やグラフィック、数値データを視覚化したインフォグラフィックスを用いることで、応募者が企業について深く理解できるようにします。
さらに、カラーリングやタイポグラフィーも企業文化に合わせて慎重に選定し、全体のトーンを統一することでブランドの一貫性を高めます。
情報の整理と分かりやすさの追求
採用サイトに訪れる応募者が最初に求めるのは、企業理念や仕事内容、募集要項、採用プロセスなどの基本情報です。
それらの情報は整理されており、目的ごとに明確に分けて表示することが重要です。
現役社員のインタビューや最新のニュース、社内の雰囲気を伝えるコンテンツなどを取り入れることで、応募者は企業文化をより深く理解することができます。
また、情報のグルーピングと余白の活用を意識することで、視覚的に読みやすく、探している情報に素早くアクセスできるようになります。
採用サイトの情報構成

採用サイトを作成すれば採用難が解決するわけではありません。
デザインに注目しがちですが、効果的な採用サイトを作るためには、まず採用戦略をしっかりと練り、ターゲットに合ったコンテンツ設計が重要です。
目的と役割を明確にする
採用サイトを作成する際は、まず目的と役割を明確にし、どのような求職者をターゲットとするのかを定めることが重要です。
新卒採用なら、学生が仕事内容や企業の魅力を理解しやすいコンテンツが必要です。
中途採用なら、キャリアアップの情報を充実させ、社会人経験者に響く内容を意識しましょう。
また、世代ごとの価値観の違いを踏まえ、ターゲットに合った情報設計を行うことも重要です。
採用ペルソナを作成し、採用チーム内で共有することで、より効果的な採用戦略につなげることができます。
求職者の関心を引くファーストビュー設計
採用サイトのファーストビューは訪問者の第一印象を決定づける重要な要素です。
企業理念を表現するキャッチコピーや社員の働く姿を写した写真を配置することで、求職者の関心を引き付けることができます。
求める人材像を明確に伝えるため、イラストや画像を活用して、求職者が自分とのマッチングを瞬時に判断できるようにします。
さらに、スクロールに連動したフェードイン表示や写真・イラストの切替、テキストの文字送り表示など動的な演出を加えることで、ファーストビューの印象を一層強化できます。
求める人材像の具体的な提示
採用サイトでは、求める人材像を具体的に示すことが重要です。
抽象的な表現ではなく、求めるスキルや経験、価値観を明確に伝えることで、求職者が自分とのマッチングを感じやすくなります。
例えば、「3年以上のWebマーケティング経験を持ち、データ分析に基づいた改善提案ができる人材」のように具体的に記述することが効果的です。さらに、アイコンやイラストを使って求める人材像を視覚的に表現することや採用実績データを活用して活躍している社員の背景を示すことも、求職者に共感を与え、理解を深めるために有効です。
データや数値を活用した説得力の向上
採用サイトでは、データや数値を活用することで説得力を高め、求職者の信頼を得ることができます。
「数字で見る○○」の形式を取り入れることで、企業の強みや特徴を具体的に示すことができ、他社と差別化が図れます。
例えば、売上高や社員の平均勤続年数、男女比率、平均残業時間、産休・育児休業取得者数などを明確に数値で伝えることで、求職者に企業の成長性、働きやすさ、福利厚生を分かりやすく伝え、安心感を与えることができます。
また、研修制度や評価制度に関するデータ(例:「年間研修時間は1人あたり平均50時間」)を紹介することで、企業の人材育成への取り組みを示し、求職者に成長の機会を感じてもらえます。
グラフやチャートを使うことで、情報を直感的に理解しやすくすることも効果的です。
情報量と見やすさのバランスを取ることで、求職者が魅力を感じやすい採用サイトが作れます。
時代が変わっても絶対必要な4つの基本コンテンツ

どんな時代でも、求職者が求める基本的なコンテンツがあります。
会社について
一つ目は、代表メッセージや企業データ、事業紹介など会社の概要が伝わるコンテンツを用意しましょう。
採用サイトでは、「社長メッセージ」「価値観」「事業紹介」「数字で見る会社情報」などを細かく分類し、それぞれ詳しく説明します。
特に「価値観」のページでは、ミッションや行動指針に加え、社風やSDGsへの取り組みも紹介し、多角的な視点で企業の価値観を伝えられるよう工夫しましょう。
人について
二つ目は、社員インタビューや座談会などを通じて、どんな人が働いているのかが伝わるコンテンツです。
採用サイトでは、「人を知る」としてスタッフ紹介を1人1ページずつ掲載します。
さらに「新卒入社」「中途入社」などの入社経路や、職種・オフィスごとに絞り込み検索ができる機能を設け、求職者が自分に近い社員や共に働く可能性のある人を見つけやすいよう工夫しています。
採用サイトのアクセス解析でも、募集要項を除けば、スタッフインタビューが最も多く閲覧されており、求職者にとって重要なコンテンツであることが分かります。
環境や制度について
三つ目は、福利厚生や社内制度、オフィス環境がわかるコンテンツです。
「オフィスツアー」「福利厚生・社内制度」「人材育成・キャリアパス」「評価制度」の4つのカテゴリに分けて紹介します。
「福利厚生・社内制度」は、一般的には当たり前のことと思われがちですが、あえて詳細に掲載することで、求職者にとって有益な情報となり、企業の魅力を伝えることができます。
募集要項
四つ目は、給与を含む職種や仕事内容など、募集要項に関するコンテンツです。
これは採用活動において非常に重要で、最も力を入れて情報発信すべき部分です。
「募集要項」をナビゲーションで最も目立たせ、職種やオフィスごとにページを分けて掲載します。
新卒採用、中途採用、キャリア採用向けにそれぞれ異なる内容を用意し、求職者が自分に適した情報を理解しやすいよう工夫しています。
求職者が最も注目している「給与・福利厚生」については、応募直前の「募集要項」ページでしっかりと漏れなく記載することをおすすめします。
これにより、求職者の不安を減らし、応募意欲を高めることができます。
採用コンテンツの成功事例3選
定量的にも効果が出ている成功事例から、特に効果的な貢献をしていると思われるコンテンツを3つあげさせていただきます。
株式会社インターグループさんの「ターゲット層を引きつける」コンテンツ

出典:https://recruit.intergroup.co.jp/
株式会社インターグループは、国際会議の企画・運営、通訳・翻訳サービス、語学教育、人材派遣、自然言語処理など、幅広い言語関連サービスを提供しています。
同社は、採用活動を強化するために既存の採用サイトをリニューアルされました。
新卒向けには、語学だけでなく「世界を動かす瞬間での活躍」に焦点を当て、動画を活用。
中途向けには、未経験者の不安を軽減する構成を取り入れ、異業種から転職した社員のインタビューや働くメリットを簡潔にまとめられています。
求職者の応募数増加と歩留まりを解消するために、採用サイトをリニューアルされています。
仕事内容がイメージしにくい点は「仕事を知る」コンテンツで職種紹介と社員インタビューを、うまく組み合わせていらっしゃる点が成功ポイントのように感じました。
ダイキンエアテクノさんの「職種紹介」コンテンツ

出典:https://recruit.intergroup.co.jp/
求職者の応募数増加と歩留まりを解消するために、採用サイトをリニューアルされています。
仕事内容がイメージしづらいという課題に対して、「仕事を知る」コンテンツで職種紹介と社員インタビューをうまく組み合わせていらっしゃる点が成功ポイントのように感じました。
実際に、学生から「採用サイトを見て仕事内容が明確にイメージできました」といった声があり、コンテンツの効果が実証されていることがうかがえます。
コスモエネルギーソリューションズさんの「数字で見る」コンテンツ
出典:https://ces.cosmo-energy.co.jp/recruit/data/
採用サイトのリニューアルにより、PV数が約7.5倍、ユーザー数も4倍に増加しました。
就活生からは「コスモエネルギーソリューションズという会社が理解できた」「丁寧な会社だと感じた」といった声が上がっているようです。
この効果に寄与した要素の一つが、「数字で見る」コンテンツでしょう。
求職者が知りたい情報を網羅し、強みを数値でダイレクトに表現している点が成功のポイントではないでしょうか。
特に、平均勤続年数19.4年や入社3年以内の離職率0%といったインパクトのある数値は、会社の良さを端的に伝え、求職者に強い印象を与えています。
まとめ
採用サイトは、ただ情報を掲載するだけではなく、求職者が入社後の姿をイメージできる内容が重要です。
サイトの目的やターゲットを明確にし、実際の活用シーンを想定して制作することで、応募率や内定承諾率を向上させることができます。
採用サイトは企業の存在を認知させ、信頼を得る手段であり、入社後のミスマッチを防ぎ、応募者の質を向上させる効果もあります。
デザインだけでなく、ユーザビリティや情報設計が重要で、一度作成すれば更新し続けることで企業の資産となります。
採用サイトの改善は、優秀な人材確保に直結する施策です。
株式会社ユニバースでは、採用サイト制作を含むWebサイト制作サービスを提供しています。
お気軽にご相談ください。
関連記事
この記事を書いた人
![]()
hara